犬的癌症
犬の胸腺型(縦隔型)リンパ腫ー特徴、治療法、改善方法
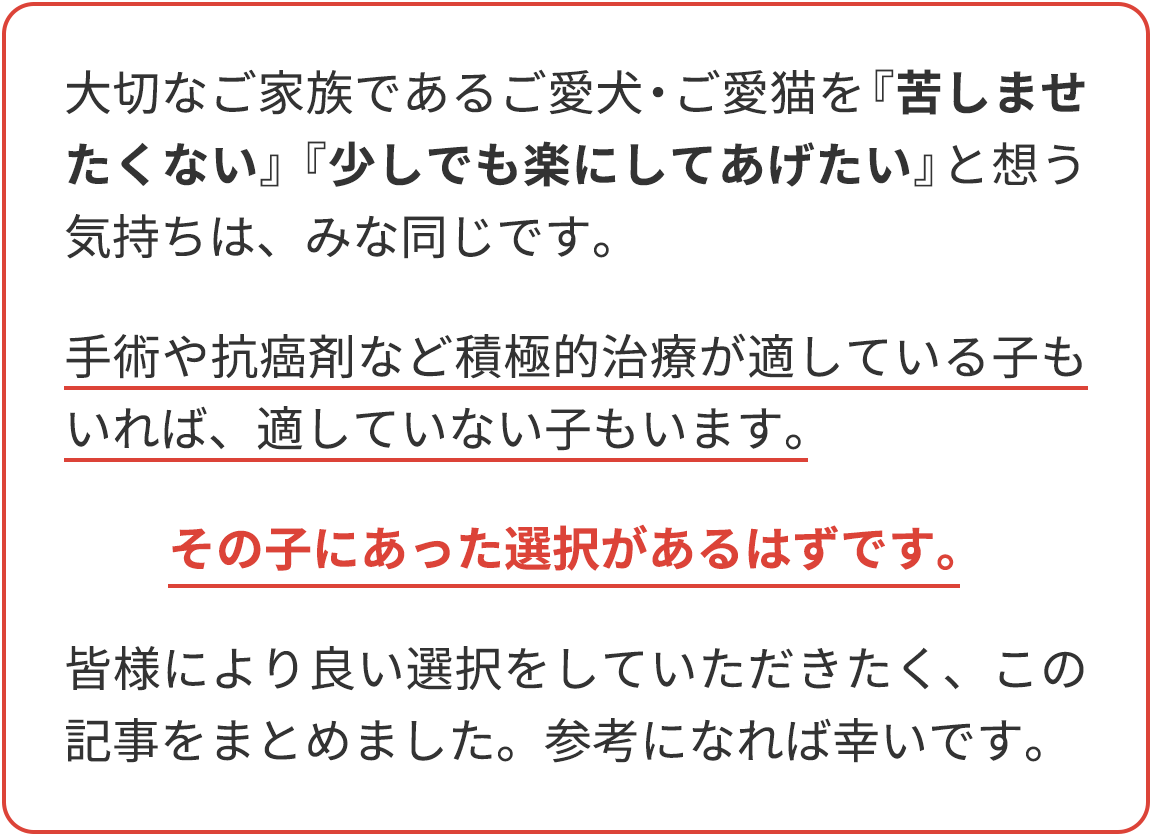
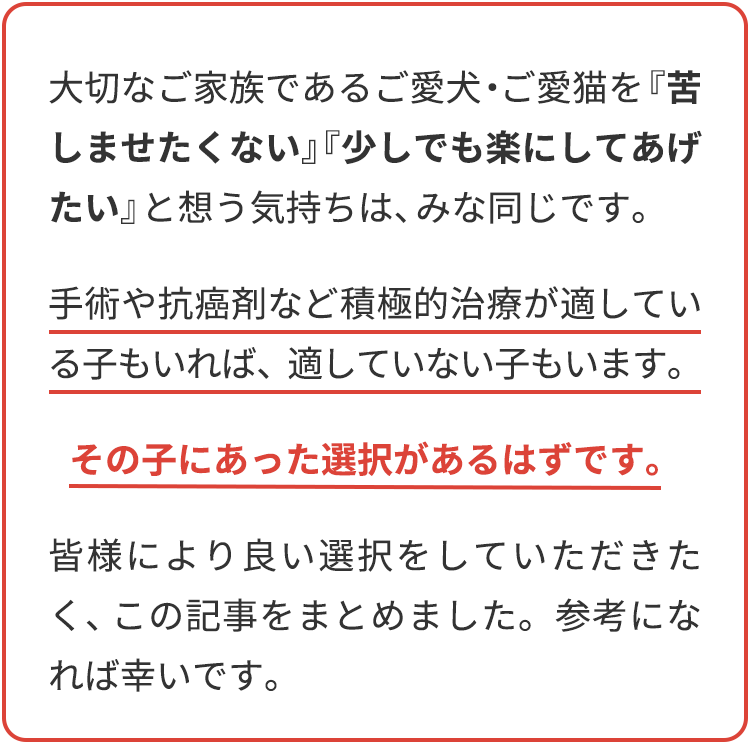
犬の胸腺型リンパ腫について
犬の悪性腫瘍の中でもご相談が多いのが、リンパ腫です。
リンパ腫は5~10歳の間に発症しやすいと言われていますが、10歳以降のシニアの子からのご相談も多くいただいております。
リンパ腫全体では発症数は相当多いですが、胸腺型リンパ腫の発症数はそれほど多くはありません。
悪性リンパ腫を発症しやすい犬種には、
・ゴールデンレトリーバー
・ビーグル
・プードル
・シェパード
などが挙げられます。
悪性リンパ腫には、その部位によって、
の5つに分類されます。
胸腺型(縦隔型)の発症率は、悪性リンパ腫のうちの2%以下と言われています。
また上記の分類とは異なりますが、お腹の中(腹腔内)に発生するリンパ腫もあります。
胸腺型(縦隔型)リンパ腫について
胸の中にある胸腺という場所に腫瘍細胞が増殖したり、縦隔と呼ばれる左右の肺と胸椎、胸骨に囲まれた空間に発生したリンパ腫を指します。
胸腔内に発生するため、咳や呼吸困難、呼吸促迫、開口呼吸などの呼吸器症状が見られます。
進行すると、嘔吐や下痢などの消化器症状も見られるようになります。
また、他のリンパ腫と違い、高カルシウム血症を併発しやすいのも特徴です。
胸腺型(縦隔型)リンパ腫の検査法・治療法
悪性リンパ腫の確定診断には、腫大している場所から細胞を抜き取る(針生検・バイオプシー)方法と、手術によって組織を取り出す方法があります。
腫大部が大きい場合には、針生検でも十分な細胞を抜き取ることが出来ますが、腫大部が小さいことなどによって細胞が十分量確保できなかった場合には、誤った診断結果が出ることもあります。
リンパ腫が確定しないことには、抗癌剤などの積極的治療は開始できません。
進行が早いが抗がん剤が効きやすい『低分子型』『B細胞性』、進行は遅いが抗がん剤が効きにくい『高分化型』『T細胞性』の分類も重要となります。
「無治療なら余命は1~2ヶ月」と言われると、つい獣医師にゆだねるしかないと考えてしまいがちですが、飼い主様の取り組みこそが重要なのです。飼い主様の取り組みは治療効果を大きく左右し、予後に影響を与えます。
「抗癌剤治療を受ければ半年、受けなければ1~2ヶ月」と言われたら、それは抗癌剤が良く効いて、副作用も少なかった時に限る話です。
抗癌剤治療を受ければ必ず延命できるのか、副作用で元気がなくなってしまう事は無いのか、効果は必ず得られるのかなど獣医師に確認されてみることをお勧めします。
胸腺型リンパ腫の予後改善のために
胸腺型リンパ腫と診断された場合、治療の中心は抗癌剤(化学療法)になります。
獣医さんの中には、犬は抗癌剤に強いとか、副作用が出にくいなどと説明をすることがあるようですが、私たちに相談いただく飼い主様から状況を伺う限り、または弊社と懇意にしている獣医師と話をする限り、この説明は正しくないと思います。
抗癌剤治療を受けてから食欲が低下したり、動きが悪くなったり、脱毛が増えたり、、、
これらの症状がみられたら、ほぼ抗癌剤の副作用が原因だと考えた方が宜しいと思います。
抗がん剤治療を開始すれば体力・免疫力はほぼ確実に低下します。
獣医師の先生から副作用は軽いからと言われて、元気になってもらいたくて治療を受けたのに、抗癌剤治療を受けてからぐったりしてしまった。。。
ということにならないように、免疫対策はしっかりと取り組むことをお勧めします。
まずは良い食事を与え、副作用で治療をリタイアしないための体力をつけてください。そして免疫を落とさないようにしましょう。
事実、しっかりと食事の見直しをし、免疫対策や肝臓のケアをして、さらに炎症を抑えるなど総合的な対策を行っていただくことで、抗癌剤のダメージがそれほど出ずに、獣医師から言われた余命を大幅に過ぎても元気食欲を維持できている例は決して少なくありません。
本来は免疫力ががん抑止の主役であり、実は抗がん剤はその補助にすぎません。免疫対策に代替療法やサプリメント(コルディ)を検討してください。
さまざまな治療の「いいとこ取り」に可能性があると思います。
抗がん剤だけに頼るのではなくそれを補完する治療を組み合わせていくことが大切だと思います。

