猫的癌症
猫の肥満細胞腫 ― 特徴、治療法、改善のヒント
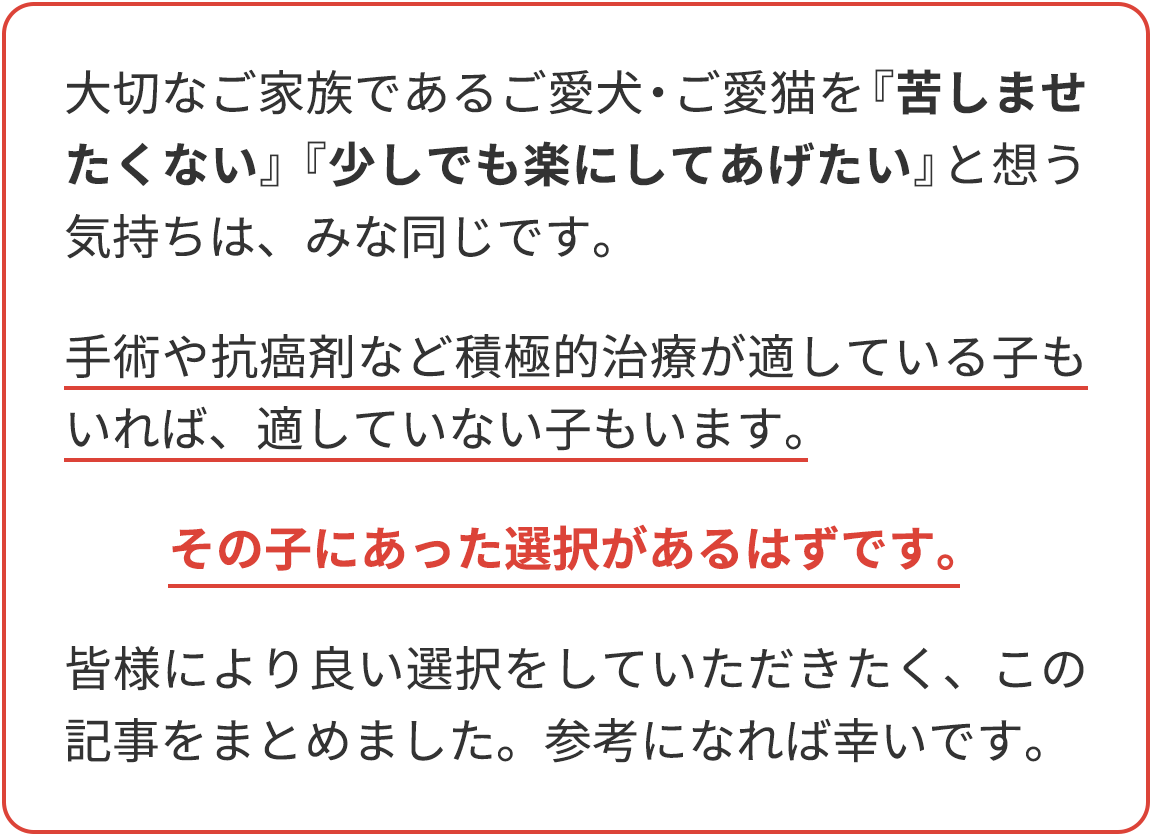
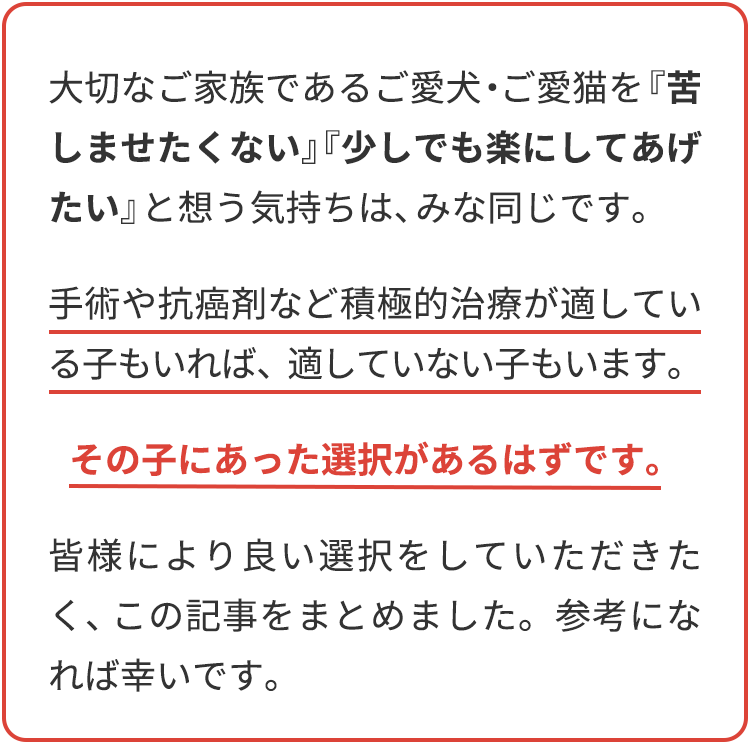

猫の肥満細胞腫とは?
肥満細胞腫は人間にはほとんど発生しませんが猫では頻繁に発生する悪性腫瘍で、猫に発生する悪性腫瘍の中では2番目に多いと言われています。
皮膚に発生する悪性腫瘍には肥満細胞腫の他に扁平上皮癌、メラノーマ、皮膚型リンパ腫や血管肉腫、線維肉腫などがあります。
猫の肥満細胞とは?
その名前から肥満との関係を連想するかもしれませんが、直接的な関係はありません。顕微鏡で見ると細胞が膨らみ太って見えるために、肥満細胞という名前が付けられています。
肥満細胞は白血球のひとつで、ヒスタミンという物質を放出する機能を持っています。ヒスタミンは炎症や免疫反応に関わりますし内臓の働きにも影響を与えます。
花粉症ではアレルギー症状を引き起こす物質として、ヒスタミンに悪いイメージがあるかもしれません。ですが鼻水や涙が出るのは体に侵入する異物を排除するための防御反応です。
肥満細胞の働きにより、生体は守られているのです。
なお肥満に関わるのは細胞内に脂肪を溜め込んでいる脂肪細胞ですので、脂肪細胞と肥満細胞腫との直接的な関わりはありません。
猫の肥満細胞腫の原因
猫の肥満細胞腫の原因は、現時点でまだはっきりとはわかっていません。
欧米では遺伝的にシャム猫のように特定の品種では若い時から皮膚型肥満細胞腫の発生が認められることがあるため、品種や遺伝による要因もあるのではないかと考えられています。
他には、身体のあちこちに多発する肥満細胞腫・多発性皮膚型肥満細胞腫では猫エイズ(猫免疫不全ウイルスFIV)と関係があるのではないかと言われています。
猫の肥満細胞腫の種類
猫の肥満細胞腫は肥満とは関係がなく、免疫を担当する肥満細胞(マスト細胞)に発生する腫瘍です。
猫に発生する肥満細胞腫は主に頭部や首のまわりなどの皮膚に発生する「皮膚型肥満細胞腫」と脾臓や肝臓、小腸などの内臓に発生する「内臓型肥満細胞腫」があります。
悪性の肥満細胞腫だった場合は命にかかわってくる病気です。手術適応がある場合には早めに手術を受けることをお勧めします。しかし手術で取りきれたように見えても再発・転移してしまう事は珍しくありません。
身しこりが肥満細胞腫かどうかは動物病院で検査を受けなければ判断できません。
皮膚型肥満細胞腫の特徴
皮膚型肥満細胞腫は肥満細胞腫の中で特に発症率が高い病気です。
皮膚型肥満細胞腫は、主に頭部や耳、耳の付け根、足等の体表の脱毛したところに1ヶ所ポコッと小さなイボのような硬いシコリ・塊ができることもありますし、体の広範囲にぽつぽつと発生することもあります。
初期症状として特に痛みや痒みもないため、発見が遅れることもあります。
皮膚型の肥満細胞腫は良性であることが多いですが、悪性の皮膚型肥満細胞腫であれば早期の治療が必要となりますので、ご愛猫の皮膚に異常が認められたらできるだけ早く獣医師の診察を受けていただく事をお勧めします。
なお、多発性の(身体の何か所にもできる)皮膚型肥満細胞腫では猫免疫不全ウイルス(FIV)との関連も疑われています。
 猫エイズウイルス感染症・FIVの原因、予防法、治療法、克服方法
猫エイズウイルス感染症・FIVの原因、予防法、治療法、克服方法
内蔵型肥満細胞腫の特徴
一方の内臓型肥満細胞腫は、体表ではなく内臓に発生する病気です。
内臓に発生するため肥満細胞腫が発生してもすぐに気が付く事ができず、発見が遅れがちです。また内蔵型肥満細胞腫の90%程度が悪性で発見が遅れた場合の治療を難しいものにしています。
内臓型肥満細胞腫では、腫瘍が発生した部位により軽度の下痢を起こしたり嘔吐が観られることがあります。元気食欲がなくなっていったり体重が減少していったりすることもあります。
元気食欲がなくなったり、体重が減ったり、お腹を触るとしこりが触れることもありますし、痩せてきたのに腹部だけはポコッとしていることもあります。
内臓に発生する肥満細胞腫は悪性度が高いものが多いので上記症状が認められたら早めに動物病院を受診し診察を受けられることをお勧めいたします。
猫の肥満細胞腫の症状
肥満細胞腫が皮膚にできる「皮膚型肥満細胞腫」では顔(頭)や頸部(首)での発生が多いですが体幹、四肢(脚)での発生もあります。内臓に発生する肥満細胞腫は脾臓や肝臓、小腸等への発生が多く認められます。
上にも書きましたが、皮膚型肥満細胞腫の主な症状は体表に硬い塊ができたり、複数個所にぶつぶつができたりします。
内蔵型肥満細胞腫の主な症状は、下痢や嘔吐、食欲不振、体重減少、お腹のシコリ、腹部の膨張などです。
また肥満細胞腫ではヒスタミンなどの物質が大量に放出されます。ヒスタミンは生命活動に必要な物質ですが、多くなりすぎると様々な問題を引き起こします。アレルギー反応が起こりやすくなったり、胃酸を増やして胃潰瘍を起こしたりします。肺に障害が出て呼吸困難を引き起こすこともあります。これらはQOL(生活の質)を著しく低下させます。場合によっては生命を危険にさらします。
猫の肥満細胞腫の検査
細胞診
細胞診とは、癌化していると思われる部分に針を刺すなどして一部採取し、顕微鏡で検査する方法です。細胞診では麻酔を使わず、あるいは局所麻酔で細胞を採りますので猫の身体への負担は少ないのですが、針を刺す部分は小さいため癌細胞を採取できない事も珍しくありません。
そのため、確実な診断はできない可能性もあります。
生体検査、組織検査
生体検査・組織検査は組織を一部切除し、顕微鏡で詳しく調べる検査方法です。広い範囲の組織、例えば手術で切除した組織を詳しく調べますので信頼性の高い検査です。
血液検査・腫瘍マーカー検査
猫が癌を患うと血液の成分に異常が現れることがあります。また抗癌剤治療に耐えられる状態なのかを調べたり、全身状態を調べるためにも血液検査を行うことは多いようです。
画像検査
レントゲンや超音波(エコー)、CTなどの機器を使い、画像をとって行う検査です。
内臓にできる癌では画像検査は有効ですし、転移の有無なども検査でわかります。
ただ画像検査だけで癌を確定することはできませんし、また、微細な癌などは画像検査で見つからない事もあります。
猫の肥満細胞腫の治療
肥満細胞腫は手術で取りきれるかどうかが予後を大きく左右します。もし手術で癌を取りきれずがん細胞を取り残すと、高確率で再発してしまう悪性度の高い癌です。
見た目だけで肥満細胞腫が良性なのか悪性なのかを判断することは難しいため、手術により腫瘍を切除し病理組織検査を行います。
手術-猫の肥満細胞腫の治療
猫が肥満細胞腫になったときに第一に優先される治療は手術です。腫瘍だけでなく、周囲をできる限り広く切除します。それは肥満細胞腫(がん細胞)が取り残されてしまうと再発が起こりやすいからです。もし再発してしまうと一般的に治癒は極めて困難になると考えられています
取りきれないとわかっていても手術することがあります。肥満細胞腫からヒスタミンなどが大量に放出されるため、体の不調を招きます。手術で腫瘍を減らすことで、症状が軽減することがあるのです。因みに症状軽減目的で行う手術を姑息手術(こそくしゅじゅつ)と言います。
手術にかかる費用は、術前・術後の検査費用や入院費そして点滴などのお薬代の合計で10万円以上~は必要になると思います。
抗がん剤-猫の肥満細胞腫の治療
肥満細胞腫の治療として化学療法が行われることがあります。
化学療法とは抗癌剤治療の事です。
抗がん剤は血液の流れに沿って全身に作用するため、腫瘍が広がりすぎて手術で取りきれない場合に行われます。
しかし猫の肥満細胞腫における抗がん剤などの化学療法の効果は証明されていませんし、費用も高額になりますので使用する際は腫瘍専門医に相談するのが良いでしょう。
また抗癌剤治療は厳しい副作用が出る可能性があることは覚悟しておかなくてはなりません。
そのため、高齢の猫や体力の低下した猫では抗癌剤治療を行わない方が良いとおもいますし、実際に積極的に抗癌剤をやらない獣医師も少なくありません。
化学療法を行うには、抗癌剤代のほかに副作用を抑える薬、そして検査費用などが必要になりますので、毎月の費用はおおよそ3-4万円~と決して安くはありません。
放射線-猫の肥満細胞腫の治療
放射線治療は大学病院など設備の整った施設で行われることがあります。基本的に放射線治療は手術と同じく、局所的な治療法です。もし広域に強い放射線を当てれば被爆により正常な組織まで障害されてしまいます。また麻酔も必要となりますし、被爆の問題があるため何度も繰り返し治療を行うことはできません。
放射線治療に対応した施設は少なく、治療費も高額です。
1回の治療がおおよそ3-8万円、一週間に3-5回、それを4週間ほど続ける(合計は12-60回の照射)になりますので、費用は40万~100数十万と非常に高額になってしまいます。しかも転移した場合には効果は限定的ですから、治療に際しては獣医師と料金の事や期待できる効果について良く話し合う事をお勧めします。
その他治療法-猫の肥満細胞腫の治療
手術で取り切れなかったり、切除不能な肥満細胞腫の時に使用されるのがステロイド(プレドニゾロン)ですが、効果はあまり期待できません。
脾臓に肥満細胞腫があり、脾臓摘出を検討している場合には、術後のステロイド投与は禁忌です。
また、肥満細胞腫の場合には強い炎症が起こるため、炎症を抑えるためにクリルオイルの使用をお勧めいたします。
猫の肥満細胞腫を放置するとどうなる?
上にもまとめましたが、手術費用や抗癌剤治療の費用、そして放射線の治療費などは高額になるため、動物病院の受診をためらう方もいらっしゃいます。
また、皮膚型肥満細胞腫はただのできもののように見えるため、特に病院に連れて行かずに放置してしまう事も少なくありません
しかし、肥満細胞腫は悪性腫瘍、つまりは癌ですから、放置していれば進行し、やがて転移してしまいます。
普段からご愛猫に触れて何か以上に気が付いたらできるだけ早めに動物病院を受診するようにしてください。
猫の肥満細胞腫の予防法
肥満細胞腫が発生する原因ははっきりしておらず、明確な予防法はありません。
しかし肥満細胞腫を早期発見できれば手術で取りきれる可能性があります。予防法ではありませんが、日頃から皮膚のチェックを行い、定期的な健康診断を受けておく事をお勧めいたします。
また、普段と様子が違う事に気が付いたら、数日様子をみて、それでも体調が改善しないようであれば動物病院を受診し診察を受けていただく事をお勧めします。
診察を受ける際には、いつころから・どのような症状が続いているのかを伝えるようにしましょう。
簡単でも良いのでご愛猫の様子をメモに記録しておくと、時系列で説明できるので獣医師の診断の助けになると思います。
もちろん「しこり」や「おでき」が見つかっても、そのほとんどは良性であり、がんではありません。過度の心配はいりませんが、動物病院で診てもらえば万が一という不安がなくなります。
なお肥満細胞腫は高齢になるほど多く発生しますので、免疫力の低下と肥満細胞腫の発生率の上昇には関係があると思われます。日頃の免疫ケアが予防に役立つと思います。
ご愛猫の肥満細胞腫の予後改善方法
肥満細胞腫では、まず手術による腫瘍の摘出が第一選択ですが、見つけられなかったがん細胞が再び増殖する可能性があります。
コルディM/コルディG/コルディフローラ等を併せて与えていただく事で免疫力をアップさせ、肥満細胞腫の予後改善・再発防止にお役立てください。
また周辺に広がっていたり、遠隔転移がある場合、手術だけで対処するのは困難です。そのような進行がんであってもコルディがお役に立てるケースはあります。西洋医学では対処できないとわかっても、諦めてしまうのはまだ早いと思います。
実際、肥満細胞腫のため余命宣告を受けてしまった猫の元気食欲を長期に維持している例もあります。
もちろん予防においても、安全性の高いコルディM/コルディG/コルディフローラは安心して使うことができます。医薬品のような副作用は心配がありません。肥満細胞腫に限らず、がんは予防してしまうのが一番良い方法です。
日頃の体調維持・管理にコルディをお役立ていただければ幸いです。
 猫の癌克服-癌の種類、原因、症状、治療、癌克服のためのヒント
猫の癌克服-癌の種類、原因、症状、治療、癌克服のためのヒント
 猫の扁平上皮癌-扁平上皮癌の予後改善・対処方法
猫の扁平上皮癌-扁平上皮癌の予後改善・対処方法
 猫のメラノーマ・皮膚がん-原因と対策・改善方法
猫のメラノーマ・皮膚がん-原因と対策・改善方法
 猫の皮膚型リンパ腫-特徴、治療法、改善のヒント
猫の皮膚型リンパ腫-特徴、治療法、改善のヒント
 猫の血管肉腫の治療法、治癒・延命・克服方法
猫の血管肉腫の治療法、治癒・延命・克服方法
 猫・犬の線維肉腫
猫・犬の線維肉腫

